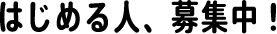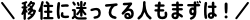奈良時代に創建され、「智堂光紹禅師」が曹洞宗として開いたという宗光寺。願いを聞いてくださるという願掛地蔵をはじめ、地域住民の心の拠りどころとして長きにわたり親しまれています。今回お話を伺うのは、その宗光寺で現在副住職を務めている押川さんです。由緒あるお寺に生まれ、周囲の期待を感じながらも、東京で夢を追いかけた20代。「寄り道があったからこそ、今の自分があると思える」 。そう噛み締めるように言葉を重ねた押川さんの半生を追いかけます。
貧乏も苦ではなかった
夢を追いかけた青春の日々
押川さんは高校まで西都市で過ごし、大学で上京。曹洞宗と関係の深い駒澤大学で、本格的に仏教を学び始めました。「住職になる心づもりはなく、刺激を求めた上京だった」と苦笑いしつつも、初めてきちんと触れた仏教の教えは心に響いたと言います。「例えば、人はなぜ悩み苦しむのか。その苦しみを払拭するためには、どのような心がけで人生を歩めばよいのか。何かを崇拝するのではなく、いかに自分の歩く道を切り拓くか。仏教にはそうしたことが書かれていたんです。とくに『我』への執着を手放すという教えに感銘を受けたことを覚えています」。



大学2年生の頃から、押川さんはある映画監督のアシスタントとして映画づくりに携わるようになりました。子どもの頃から大の映画好きで、西都市でもレンタルビデオショップに通い詰めていた押川さんにとって、それは夢の世界に大きく近づくことでもありました。監督が手書きした脚本の清書や、撮影現場での制作、雑務まで、寝る間を惜しんで何でも引き受けたといいます。自主制作だったこともあって、報酬はゼロ。撮影のない日には日雇いの仕事をしてなんとか繋いでいるギリギリの生活でしたが、「この日々がずっと続けばいいなと思えた」と当時を振り返ります。「住んでいた家も築70年ほどの古いアパートだったのですが……それでも不思議と苦ではなかったです。同じ夢を共にする仲間と夜な夜な飲んで語らい、本当に楽しかった。何かを表現をしたいという熱意があったから動けたのだと思います」。
気がつくと経典を片っ端から読んでいた
そんな輝くような青春の日々にも、やがて終わりが近づいてきます。大学卒業後もしばらくの間は映画制作を続けていたものの、一人、また一人と仲間が離脱。そもそも、自分は何を描きたいのか。描けたとして、その表現は世間に認められるのか。雲行きが怪しくなる中、東日本大震災の影響がさらなる追い打ちとなり、映画の世界から一度離れる決意が固まりました。
「(仏道を歩むための)修行をすれば強くなれるかもしれない、人様に手を差し伸べられる人間になれるかもしれない、と思ったんです。修行に入る際は父を通じてお寺へ連絡するのですが、父は映画づくりにふける私にカンカンでしたから、もちろん反対されました。そんな安易な気持ちじゃ務まらないと。父を1週間ほど説得し、師事していた監督にもご納得いただいて、2013年の3月から福井県の永平寺というお寺で修行に入らせていただくこととなりました」。



しかし、話はここで終わりません。朝3時に起床する修行生活に慣れ、坐禅やお勤めに精を出す一方で、押川さんの心には映画づくりへの諦めきれない想いが芽生えてきたのです。修行を経た今であれば、ひょっとしたら理想の映画が作れるのではないか。その想いに駆られ何度も懇願した末に東京に戻ったものの、映画づくりの壁は想像以上に高いものでした。
「はい……。それが、どうしても撮れなかったんです。映画づくりを辞めて修行に行くと言って、やっぱり映画を撮りたいと戻ったのに、です。送り出してくれた仲間の顔を思い出して、本当に辛い日々でした。でも、そんなときに私を救ってくれたのが、やはり仏教の教えでした。気がつくと経典を片っ端から読んでいて。改めてしっかりと読んだとき、今私が抱えている悩みを解決する方法がすべて書いてあるじゃないかと気づき、ここでようやく、本当の意味で『お坊さんになろう』と決心することができました」。
お寺を気軽に立ち寄れる場所に
夢を追うなかで確かなものとなった決意を胸に西都市に戻ってから、約10年。10代の頃はテレビで見られる放送局も少なく、刺激に飢えて「このまちには何もない!」と思っていた押川さんですが、今はここにすべてがあると感じられるようになったと話します。用事を済ませてお寺に戻ると、誰かからの野菜が置いてある。目には見えづらい、人と人とのつながりが感じられるまち。そうした点に気付くことのできる感性は、迷いや葛藤を乗り越えた経験からくるものかもしれません。
最近は坐禅会や写経会に加えて、ヨガと坐禅をかけ合わせたイベントや、匂い袋のブレンドが体験できる企画などを積極的に開催。気軽にお寺を訪れてもらえるよう、様々な切り口できっかけを作ろうと工夫を凝らしています。西都市の話になったとき、開口一番「ここに骨を埋めるつもりですよ」とさらっと答えた押川さん。その言葉に、言葉以上の覚悟が感じられました。

 FROM SAITO CITY MIYAZAKI
FROM SAITO CITY MIYAZAKI